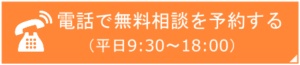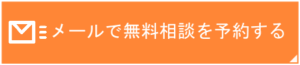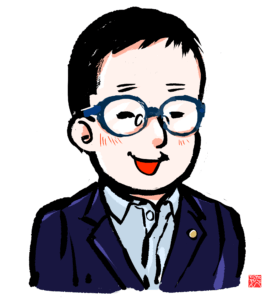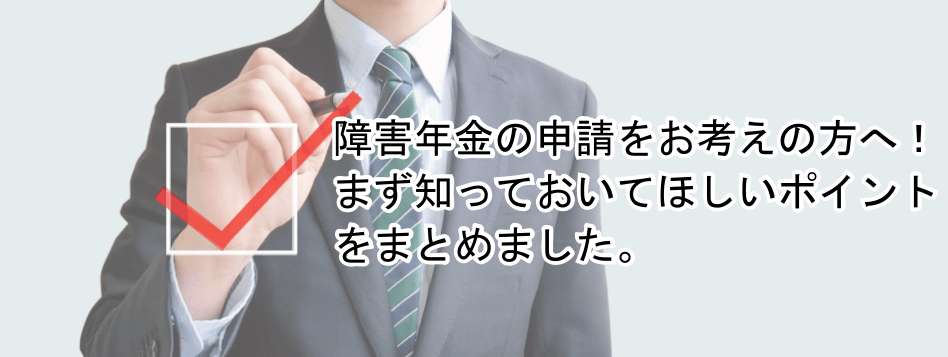
当事務所のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。
こちらのページをご覧頂いているあなたは、お怪我やご病気による障がいでこれから障害年金の手続きを検討中の本人やそのご家族、支援者の方かと思います。
今お持ちのお困りごとはどのようなものでしょうか。
〇障害年金を申請したいけれど、何から始めたらよいかがわからない…。 〇申請書類を入手したけれど、何もしないまま1か月が経過した…。 〇自身で申請をしようとしたけれど、途中で諦めてしまった…。 〇自身で申請をしたけれど、不支給決定になってしまった…。 〇障害年金の手続きを一人でするのは不安だが、誰に相談してよいかわからない…。 |
こちらのページでは、障害年金の手続きをお考えの方に向けて、社会保険労務士がポイントをまとめております。
このホームページにある情報があなたのお役に立ちましたら嬉しく思います。
障害年金の専門家として、お手続きの代行も承っております。ご自身で手続きをすすめる
もしこちらのホームページをご覧いただき、障害年金に関することで解決しないことがありましたら、お気軽にお問い合わせ頂ければと思います。
もくじ
障害年金受給の条件は3つ

要件①初診日要件
障害年金を請求しようとする病気やお怪我で初めて医療機関にかかった日(「初診日」といいます)を証明する必要があります。
証明には、医療機関から発行された書類等の客観的資料が必要になります。
初診日を特定した上で、その初診日において、以下の(1)~(3)のいずれかに当てはまることが必要です。
(1)被保険者である方(国民年金or厚生年金)
(2)次のすべてを満たす方
・60歳以上65歳未満の方
・国民年金の被保険者であった方
・日本国内に住所がある方
・老齢基礎年金の繰上げ受給をしていない方
(3)20歳未満である方
初診日の詳しい解説はこちらの記事をご覧ください。
要件②保険料納付要件
障害の初診日の前日において、以下の(1)~(2)のいずれかに当てはまることが必要です。
但し、初診日の時点で20歳未満の方は納付要件を問われません。
(1)20歳から初診日の属する月の前々月までの期間に3分の1以上の未納がないこと
(2)初診日の属する月の前々月までの1年間に未納がないこと
※保険料納付要件の図を使った解説はこちらの記事をご覧ください。
要件③障害状態要件
初診日から1年6ヶ月が経過した日(「障害認定日」といいます。)から65歳のお誕生日の前々日までに、国が定める障害認定基準に当てはまることが必要です。
障害認定基準の目安をおおまかに説明すると以下のようになります。
| 等級 | 障害状態 |
| 1級 | 障害により常に他者の介助が必要。労働は不可。 |
| 2級 | 障害により日常生活の多くに他者の介助が必要。労働は不可。 |
| 3級 | 障害により労働に制限がある。 |
こちらはあくまでも目安です。
障害年金の対象となる傷病名は多岐に渡るため、傷病ごとに細かく基準や審査方法が定められています。
<主な傷病の認定基準>
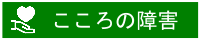 | 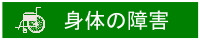 |
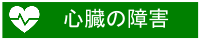 | 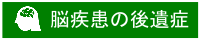 |
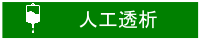 | 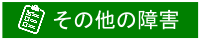 |
障害年金 もらえる金額(年額)は?

障害年金の金額は、初診日の時点で加入していた年金制度(国民年金or厚生年金)や障害等級(1〜3級)で変わります。
●初診日が国民年金の方:障害基礎年金
●初診日が厚生年金の方:障害厚生年金
※配偶者の扶養に入られている方は「初診日が国民年金の方」に該当します。
なお、このページに記載の金額は年額です。(障害手当金を除く。)
障害基礎年金(2024年4月1日現在)
| 1級 | ○昭和31年4月2日以後生まれの方 1,020,000円(+子供がいる場合は子供の加算額) ○昭和31年4月1日以前生まれの方 1,017,125円(+子供がいる場合は子供の加算額) |
| 2級 | ○昭和31年4月2日以後生まれの方 816,000円(+子供がいる場合は子供の加算額) ○昭和31年4月1日以前生まれの方 813,700円(+子供がいる場合は子供の加算額) |
子供の加算額
| 1人目・2人目の子 | (1人につき) 234,800円 |
| 3人目以降の子 | (1人につき) 78,300円 |
※子とは次の者に限ります。
○18歳年度末(高校を卒業する年齢)までの子供
○障害等級1級または2級の障害状態にある20歳未満の子供
障害厚生年金 (2023年4月1日現在)
障害厚生年金の額は、厚生年金に加入していた期間の長さ、納めていた保険料の額(給与の額)などで変わります。
なお、厚生年金加入期間の短い方の年金額が極端に低くなってしまうのを防ぐため、加入月数300月未満のときは、300月として計算します。
また、3級の年金額には最低保障額が設けられています。
| 1級 | 報酬比例の年金額×1.25+障害基礎年金1級の年金額(子供の加算含む) |
| 2級 | 報酬比例の年金額+障害基礎年金2級の年金額(子供の加算含む) |
| 3級 | 報酬比例の年金額 ※3級には最低保証額があります。 ○昭和31年4月2日以後生まれの方 612,000円 ○昭和31年4月1日以前生まれの方 610,300円 |
| 障害手当金 (一時金) | 報酬比例の年金額×2年分 ※障害手当金には最低保障額があります。 ○昭和31年4月2日以後生まれの方 1,224,000円 ○昭和31年4月1日以前生まれの方 1,220,600円 |
配偶者の加算額
| 配偶者の加算額 | 234,800円 |
*障害年金は非課税です。所得税や住民税を控除されることはありません。
ご相談から受給まで

まずはお電話またはメールでご連絡ください。
当事務所では、障害年金の手続きをお考えの方からのご相談を初回無料で承っています。
基本的には電話やメールでご予約を頂き、お会いして、現在のご病状や生活やお仕事の状況、これまでの治療歴などをお聞きしながら、障害年金を受給できる可能性についてお話をさせて頂きます。
電話やZoomでのご相談ももちろん可能です。
障害年金を受給できる可能性についてお伝えした上で、ご自身でお手続きを進めるか、当事務所のサポートをご利用頂くかをご検討いただきます。
Q.料金は? ①着手金 11,000円(税込) ②年金が受給できた時にお支払い頂く報酬(ⅰかⅱのいずれか高い方) ⅰ.年金の2か月分+消費税 ⅱ.初回入金額の11% |
お手伝いをご利用いただく場合には、契約書と委任状の記入と押印を頂きます。
電話やZoomでご相談を頂いた場合には、ご自宅に書類を送り、記入・押印の上でご返送いただきます。
※ご来所であっても電話やZoomであっても、その場ですぐにご契約を頂く必要はございません。
ご依頼いただいた場合の流れ
①申請書類の取得・作成
私たちが医療機関に診断書や受診状況等証明書の作成依頼を行います。
ただし、診断書の作成には医療機関で検査や問診をしてもらう必要がありますので、お客様ご本人に病院へご持参いただく場合もございます。
(その場合には作成依頼の書類を一緒にお持ちいただき、スムーズに作成依頼ができるようにお手伝いいたします。)
また、書類が完成した際に受け取りも代行いたします。
※書類の作成料はお客様にご負担いただきます。
②診断書の記入内容のチェック
診断書等の書類を当事務所にて、チェックいたします。必要に応じて、医師に修正・加筆の依頼を行います。(ただし、医師の考えや症状によっては修正や加筆に応じてもらえない場合があります。)
③病歴・就労状況等申立書の作成
ヒアリング内容や診断書の内容に沿って、病歴・就労状況等申立書を作成いたします。
④障害年金裁定請求書の作成・提出
作成した裁定請求書に必要書類をそろえて、年金事務所(又は市町村役場)に提出します。提出後、年金事務所等からの問い合わせや照会は当事務所で対応いたします。
⑤障害年金の支給が決定
障害年金の決定には、裁定請求書の提出から約3~4カ月ほどかかります。 (ケースによってはもう少しお時間がかかる場合もあります)
決定されますと、ご自宅に年金証書が届きます。
⑥報酬のお支払い
日本年金機構よりお客様の口座に年金が振り込まれてから、報酬をお振込頂きます。
サポート報酬は年金の2か月分です。(さかのぼった場合は初回入金額の10%です。)
※料金の説明ページはこちらです。
⑦年金受給後の手続き
障害年金を受給すると、受給後1~5年で更新があります。
更新の際には、診断書(障害状態確認届)を提出する必要があります。
診断書の内容によって、そのまま年金がもらえたり、等級が変更(上下)したり、年金が停止になったりということが起こります。
そのため、診断書の内容が実態に合った内容になっているか、症状に関しての書き漏れがないかなどの確認が非常に重要になります。
※更新に関しても、当事務所でサポートを行っております。
最後に

こちらの記事では障害年金を受給するために知っていただきたいポイントをまとめました。
記事をお読み頂き「自分は該当するだろうか?」「該当しそうだが手続きが不安だ」等の疑問がございました、私たちに一度ご相談ください。
障害年金に関する初回のご相談は無料で承っております。
こちらの記事が、これから障害年金を申請なさるあなたのお役に立ちましたら幸いです。
執筆者プロフィール 玉置 伸哉(社会保険労務士) アルバイト時代の仲間が、就職した会社でパワハラ・セクハラ・給与未払いなどの仕打ちを受けた挙句に身体を壊したことをきっかけに社会保険労務士を目指す。 札幌市内の社会保険労務士事務所で7年間従事、うち6年間を障害年金の相談専門の職員として経験を積み2018年4月に退職。 2018年8月に社労士試験を受験(6回目)し、同年11月に合格。 2019年2月、障害年金専門のTAMA社労士事務所を開業。 障害年金に特化した社会保険労務士として、障害年金請求のサポートを日々行っております。 また、就労支援事業所様等において「30分でざっくり覚える障害年金講座」「障害年金出張相談会」を積極的に行っています。 詳しいプロフィールはこちらから |